顧問先の「組織づくり」、変化に対応できていますか?
少子高齢化による人手不足や労働力の低下、リモートワークなどの多様な働き方の広がりへの対応が迫られています。時代は、管理型マネジメントから協働型マネジメントへ移行しつつありますが、皆さんの顧問先は柔軟に対応できているでしょうか。
知識やスピードはAIが担えても、「創造性」「コミュニケーション」「コラボレーション」の部分は引き続き人が関与する必要があります。そのためにも組織の「心のはたらき」に注目しなくてはいけません。
社労士にしかできない「心のマネジメント」とは?
今回のセミナーでフォーカスするのは「心のマネジメント」です。パフォーマンスの高い組織に必要なのは、社員自身が存在に自信が持て、不安感が少ない状態で働けていることです。これを「適応感」といい、適応感の高さは「心のマネジメント」ができているかに左右されます。
心のマネジメント力が高い組織をつくるとき、必要なのは社労士が持つ人事労務の知識。就業規則、人事制度、メンタル管理などの分野の専門家が、社会から求められはじめています。
社労士が組織開発を学べば、「人の専門家」として顧問先と共創できる存在になれるのです。
セミナーでお話しすること
- 適応感を高めるための、戦略的な就業規則のつくりかた
- 中小企業は、組織開発の専門家を雇えない!社労士がどう活躍すべきか
- 社労士も本質的な役割を果たす、人事・労務+αの視点とは
- 組織開発のプロとして顧問先に関与するための具体的なプロセス
その他にも、専門家の目線をどう活かすかのヒントをお伝えいたします。
心のマネジメントという視点を持てば、よい組織の下地がつくれます。
これまでに培った学びやご経験を、顧問先の組織開発に活かすことができれば
新しいフィールドが広がるでしょう。ぜひご視聴ください。
※この動画は過去のセミナーのアーカイブです。全ての特典は終了しておりますのでご了承ください。


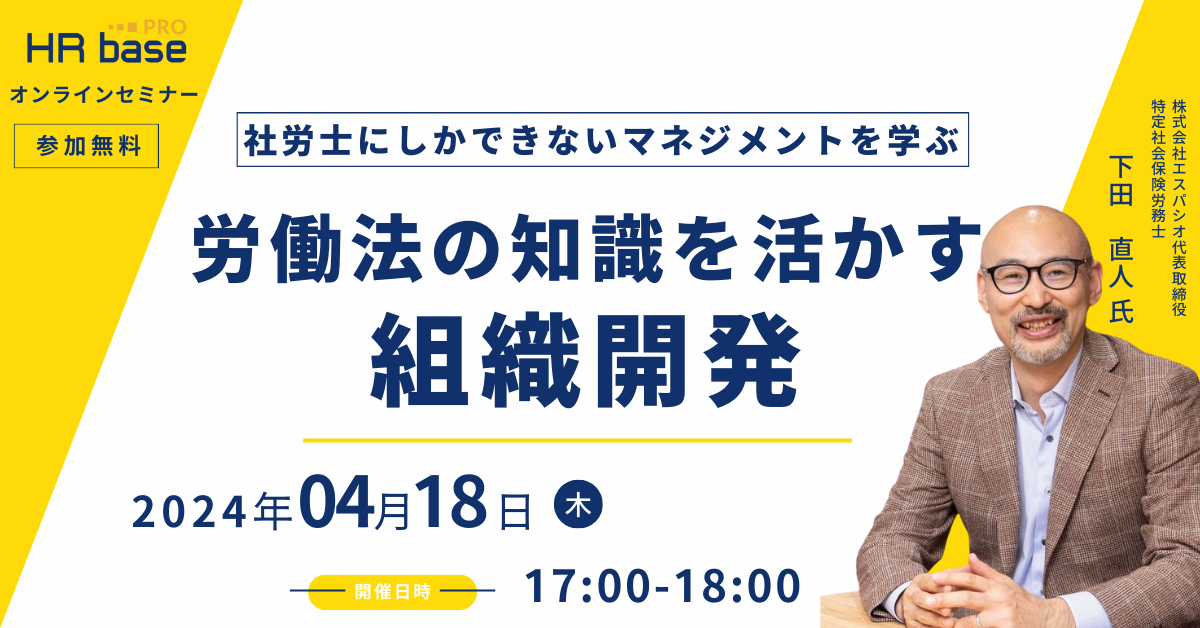
.png?width=1200&height=436&name=logo_HRbase_PRO_white%20(1).png)